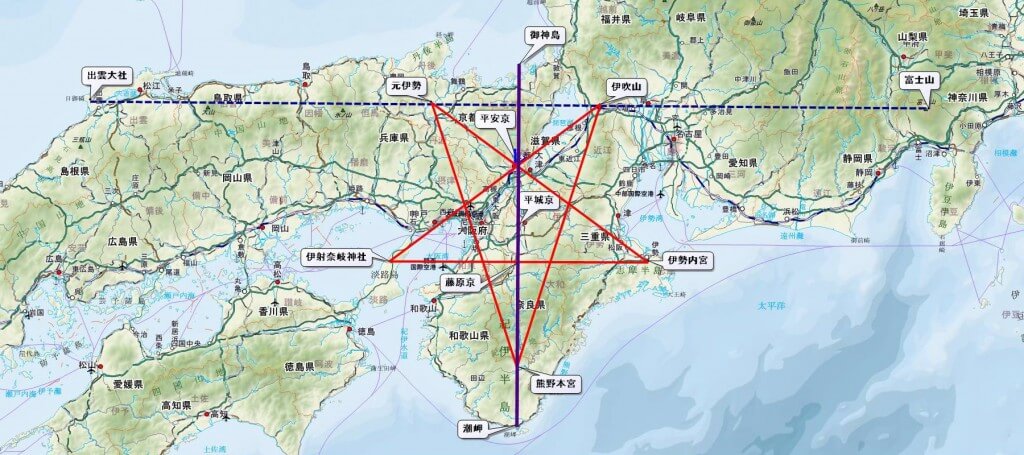21番札所太龍寺を目指して那賀川に架かる水井橋を渡った地点に石像群があります。かつてこの地にあった「水井の渡し」の関係していて、石像群の中に中務茂兵衛によって建立された弘法大師坐像も存在します。

石像群の中に中務茂兵衛由来の弘法大師の坐像があります。
中務茂兵衛義教

中務茂兵衛義教<なかつかさもへえよしのり/弘化2年(1845)4月30日-大正11年(1922)2月14日>
周防國大嶋郡椋野村(すおうのくにおおしまぐんむくのむら、現・山口県周防大島町)出身。
22歳の頃に周防大島を出奔(しゅっぽん)。それから一度も故郷に戻ることなく、明治から大正にかけて四国八十八ヶ所を繰り返し巡拝する事279回と87ヶ所。バスや自家用車が普及している時代ではないので殆どが徒歩。 歩き遍路としての巡拝回数は最多記録と名高く、今後それを上回ることは不可能に近い。 明治19年(1886)、茂兵衛42歳。88度目の巡拝の頃から標石(しるべいし)の建立を始めた。標石は四国各地で確認されているだけで200基以上。札所の境内、遍路道沿いに数多く残されている。
中務茂兵衛大師坐像がある場所と解説板

この地点は水井橋の中央部で、道幅が広くなく自動車が来た時に退避することができないため、速やかに渡る必要があります。
手前に「寺龍太」と追記された中務茂兵衛標石があり、橋を渡り切って右に曲がった先に、こちらの石像群があります。
※水井橋手前の中務茂兵衛標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【20番札所鶴林寺→21番札所太龍寺】那賀川を渡る水井橋の手前にのこされている中務茂兵衛標石

那賀川左岸(=水井橋北)にある標石と同様に「加茂谷へんろ道の会」による解説板が設置されています。
解説板によると、こちらの石像群はかつて存在した水井渡し由来のもので、昭和40年(1965)の水井橋建設に際して同地に移設されたことがわかります。
渡船場に地蔵菩薩が祀られているケースは全国的に数多く存在して、四国八十八ヶ所道中でいえば、29番札所国分寺の手前の「地蔵の渡し」や36番札所青龍寺へ向かう「龍の渡し」が思い出されます。どちらも現在は渡船としての役目を終えていますが、渡し場があった地点に地蔵菩薩が残されていて往時の役割を現在に伝えています。
当地「水井渡し」については水井橋への切り替えによって痕跡は残されていないように考えていましたが、場所を変えてかつての渡し場の存在を伝えていることを今回知りました。
地蔵菩薩が建立された文化時代

中務茂兵衛建立の弘法大師坐像は左上のものになります。
右上の地蔵菩薩も台座が高く設けられた高地蔵の形状ですが、茂兵衛さんのそれより80年近く古いもので、解説板によると文化12年(1815)の建立とあります。
文化(1804-1818)と後続する文政(1818-1831)と合わせて「化政文化(かせいぶんか)」として語られることが多い文化時代・文政時代は、江戸時代前期に興った元禄文化が上方が中心だったことに対して、江戸時代後期に興った化政文化は江戸から発信された相違点があります。富士山の絵が連想されるのはそのためですね。
どちらも町民の習俗という点が共通していて作品のジャンルは多岐に亘りますが、元禄文化は能や浄瑠璃のような芸能が代表作として紹介されることが多いのですが、化政文化は小説や錦絵など紙を用いて発信された作品が紹介されるケースが多い気がします。東海道五十三次/歌川広重や、富嶽三十六景/葛飾北斎などが化政年間の作品ですね。他國(=現在の県外)へ行くことが難しい時代にあって旅行を扱った作品がヒットしたことは、265年続いた江戸時代の中でもとりわけ泰平の世とされた化政年間ならでは特徴かもしれません。
中務茂兵衛建立の弘法大師坐像

左上の中務茂兵衛建立の弘法大師坐像を詳しく見ていきたいと思います。
この場所は歩き遍路で何度も通行して石像群があることは知っていましたが、その中の弘法大師坐像が中務茂兵衛建立のものとわかったのは、加茂谷へんろ道の会が設置した解説板を見てのことです。
中務茂兵衛建立の石像といえば、愛媛県南予の40番札所観自在寺から41番札所龍光寺の間にある柏坂の石像を思い出しましたが、そちらも同じお大師様の坐像で、どちらも茂兵衛さんのものとは知らずに通り過ぎていて、それと気付いたのがだいぶ時間が経ってからという点が共通です。
※柏坂にある中務茂兵衛建立の弘法大師坐像に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【愛媛県愛南町柏坂】四国有数の遍路ころがし道中にある中務茂兵衛建立の大師像

台座部分を詳しく見ていくと寄進者らの情報が判明します。
<弘法大師坐像台座部>
施主
備後國御調郡尾乃道●
大藤忠兵衛
●性院真空●
為大藤氏●
●●院●●●●
願主
周防國大島郡椋●
中務茂兵衛
前述の通りこちらの石像群は当地に移設されたものなので、下部が埋没気味でわかりづらい部分がありますが、施主は現在の広島県尾道市の人物で、姓は大藤氏です。姓の左右に戒名と思しきものが記されているので、その時の当主が両親を含む一家の先祖供養として建立したイメージでしょうか。
※大藤氏の寄進による中務茂兵衛標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【76番札所金倉寺近く】中務茂兵衛ゆかりの寺院にある小さな88度目の中務茂兵衛標石
左隅に記されている内容で、こちらの弘法大師坐像が中務茂兵衛由来のものとわかります。巡拝回数や建立年度が記されていないのですが、解説版によると明治27年(1894)の建立と記載されています。
以下リンクの記事の標石が明治27年の建立で巡拝回数が137度目なので、当標石を建てた際の茂兵衛さんの巡拝回数はその前後回数かと思われます。
※明治27年建立の中務茂兵衛標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
同年1月18日、熊本県で高群逸枝(たかむれいつえ/1894-1964)が誕生しています。
日本における女性史学の創設者で、24歳の時に経験した四国巡礼は九州日日新聞に「娘巡礼記」として連載されました(全105回)。女性が旅行、それも一人で旅をすることが珍しいというよりあまり良くない目で見られていた時代に経験した四国八十八ヶ所まいりは、女性目線であったり当時の遍路界の様子を知る上で貴重な作品になっています。
※高群逸枝に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【大黒山吉蔵寺】愛媛県八幡浜市に四国八十八ヶ所霊場の幻の札所?があった話
標石メモ
発見し易さ ★★★★★(※★☆☆☆☆)
文字の判別 ★★★★★(※★★★☆☆)
状態 ★★★☆☆
総評:解説板があるためこの場所を通行するとほぼ見つけることができることと、内容を把握できます。※の星の数は弘法大師坐像単体の場合で、標石ではなく坐像の台座部分に情報が記されているため、それが中務茂兵衛由来のものだと気付くのが難しいと思います。
※個人的な感想で標石の優劣を表すものではありません
【「水井橋近くの中務茂兵衛建立弘法大師坐像」 地図】