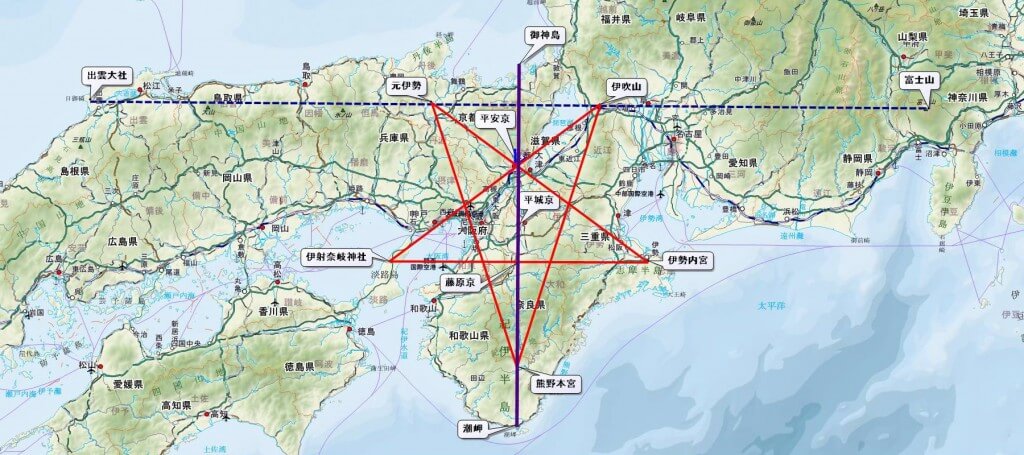香川県丸亀市の中心市街地はかつての丸亀城の城下町です。城下町の北東地点のかつて丸亀城が有していた外濠近くの旧街道沿いに遍路道を示す標石がのこされています。

この写真で標石奥の軽自動車が居る地点の左右に、かつて丸亀城外濠があり、現在この地点は緑道公園になっています。
※この標石よりも77番札所道隆寺方向のすぐ近くにある標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【77番札所道隆寺→78番札所郷照寺】旧丸亀街道にのこされている遍路道を示す標石
【77番札所道隆寺→78番札所郷照寺】地面から少しだけ顔を出している丸亀城下の中務茂兵衛標石
標石の正面に表記されている内容

こちらの標石がある地点は逆T字の三叉路で、順打ちで訪れてこちらの面を見る時は、対面よりは西から歩いて来て左横目に見る形になると思います。
<正面>
指差し
右
へんろ道
丸亀城の外濠はのちほど触れることにして、まずは標石から見ていきたいと思います。
こちらの標石が立っている道は高松から丸亀を行き来する旧丸亀街道であり、お遍路さんが通る遍路道でもありますが、標石正面の情報からはお遍路さん向けの情報提供を行う標石である印象を受けます。
丸亀街道は高松城下の常磐橋までつながっていました。
※丸亀街道の高松城下の起点に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【高松城外堀】常磐橋のふるさとからみる明治以降の高松市街地の変遷
標石の右面に表記されている内容

右面は何もないように見えますし、へこみから何か字が刻まれていたようにも見えます。
<右面>
記載なし
写真奥が西で、丸亀市街地及び順打ちのお遍路さんがやってくる方角です。
とはいうものの、現代においてお遍路さんが丸亀市内を通行するにあたり、一般的に紹介されている経路は香川県道33号高松善通寺線で、この道の南側にある片側二車線の広い道路です。
当記事で登場する標石がのこされている道は、こちらの写真でもわかるように住宅街の中の道で、旧城下町なので道路は縦横碁盤目と思いきや、所々で曲がっていたりしてわかりやすい順路ではありません。標石見学目的でなければ、前者の道を通行するほうが良いと思います。
標石の左面に表記されている内容

順打ちでこの場所を訪れると最初に目にするのがこちらの面で、こちらの石がある場所から次の札所である78番札所郷照寺まで距離約2.6kmであることを示しています。
<左面>
七拾八番札所貮拾四丁
七拾八番札所→78番札所郷照寺
貮拾四丁→24丁→約2,600m
標石があるのは丸亀市ですが、78番札所郷照寺があるのは隣の宇多津町です。写真中央上あたり、標石上部の右に少しだけ山が写っているのが見えますが、その山(青ノ山/標高224m)のふもとに78番札所郷照寺があります。
標石の先の道路が変則交差点になっていますが、そちらにはかつて丸亀城外濠があったためです。
丸亀城外濠跡につくられた東汐入川緑道公園

戦前は存在した丸亀城の外濠ですが、埋め立てが始まったのが昭和23年(1948)で、現在その痕跡はほとんどの場所で失われています。
標石の先にあるかつての丸亀城外濠へやって来ました。濠が埋め立てられていたとしてもこの場所のように緑道公園になっていれば、ここがかつての外濠だったことをうかがい知ることができますが、丸亀の場合はほとんどの場所が道路や宅地に転用されて、その痕跡を訪ねることが難しくなっています。

ここまで当地点を外濠と申し上げてきましたが、正確には外濠から流出する東汐入川と呼ばれる河川が流れていたようです。
城のお堀といえばおおよそ四角形を想像されると思いますが、丸亀城外濠も概ねその形状でした。その北東(地図では右上)地点から流れ出ていたのが東汐入川で海と繋がっていたようです。その名の通り、満潮時には海水が外濠へ逆流してきていたのではないでしょうか。そもそもが東部(=右側の一辺)は東汐入川に手を加えたもの、西部(=西側の一辺)は西汐入川に手を加えたものが、丸亀城外濠と考えることもできます。

これまでこの場所を歩き遍路や私用等で何度も通っていますが、かくいう私も、今回外濠の痕跡を探索しに来て初めてここが外濠ではなかったことを知りました。
こちらの緑道公園には「旧渡し場」であることを知らせる標石が立っています。この名称は奥に見えている歩道橋の左に「渡場」というバス停があるので聞いたことがありましたが、てっきりその先に流れている香川県唯一の一級河川である土器川を渡る渡船由来のものだと思っておりましたが、どうやら東汐入川を渡していた渡船のことを指すようですね。
考察するに、濠は外敵の侵入を防ぐためのものなので、ある程度の水深を必要とします。そしてみだりに橋を架けてしまってはその意味がなくなるので、丸亀城外濠と繋がっている東汐入川を渡るためには、渡船を利用せざるをえなかったのかなと思いました。おそらくそれは明治時代以降に解消されていったことと思いますが、その時代に四国八十八ヶ所を回ったお遍路さんは「たったこれだけの距離なのに」と思いながら渡船利用を余儀なくされていたのではないでしょうか。

東汐入川緑道公園と丸亀城(写真中央)の位置関係はこんな感じです。
丸亀城外濠の北東角および東汐入川が流れ出ていた場所は、写真左の歩道橋がある地点です。ここには現在、香川県道33号高松善通寺線(旧国道11号)が通っています。
この場所に最初にできた近代交通は、昭和3年(1928)1月に敷設された琴平参宮電鉄(琴参)の坂出線で、後に国道11号に相当する道路(現・県道33号)が通ったようです。この場所に敷設された鉄道・道路は、共に丸亀城外濠北側の一辺を埋め立てた土地が転用されたようです。
琴参の鉄道線は戦争を乗り越えて人々を運び続けましたが、業績不振により昭和39年(1963)9月に全廃されました。この付近の跡地は道路の拡幅に用いられたようです。
※琴平参宮電鉄に関しては、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【香川県琴平町】金刀比羅宮行き鉄道4社の「こんぴら鉄道競争」の痕跡である鉄道立体交差
※丸亀城に関して、以下リンクの記事で詳しく紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。
【丸亀城】日本一高い石垣と大きく見える工夫が施された現存天守
※丸亀城の外濠の痕跡に関して、以下リンクの記事でもご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【香川県丸亀市】現存十二天守のひとつを有する「丸亀城」の旧外濠の痕跡を訪ねる
標石メモ
発見し易さ ★★☆☆☆
文字の判別 ★★★☆☆
状態 ★★★☆☆
総評:現代の地図では遍路道として紹介されていない場所にあるので、存在を知らなければ通ることは稀なように思います。石の劣化が見られるものの字の判別が困難と言うほどではなく、記載内容を把握することができます。
※個人的な感想で標石の優劣を表すものではありません
【「丸亀城外濠跡近く標石」 地図】