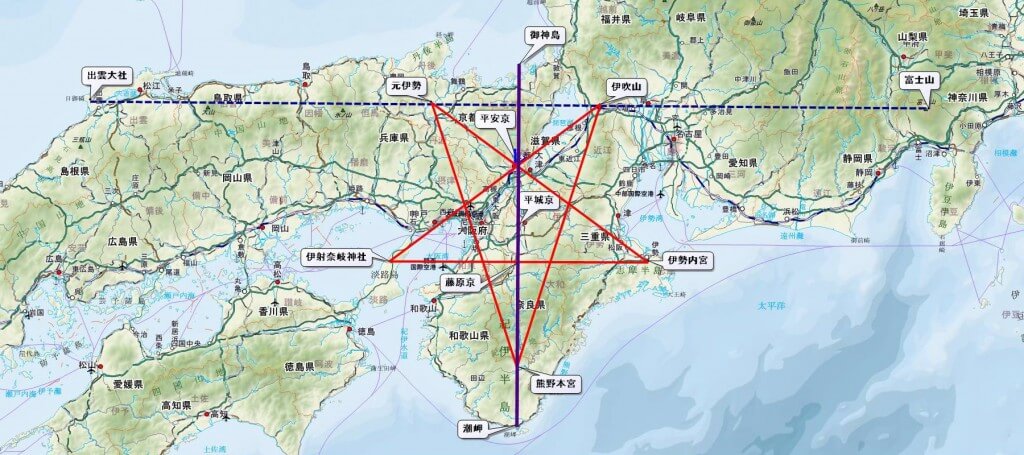徳島県徳島市の市街地に位置する「蔵本駅」は、路線規模や乗降客数を考えると持て余し気味な長いプラットホームを有しています。長いプラットホームに秘められた歴史を紐解いてみます。

近くに徳島大学医学部があり学生の街が広がっている徳島市街地にある蔵本駅をご紹介します。
徳島県内の鉄道駅が近い札所

路線図で蔵本駅を確認すると、徳島県の中心駅である徳島駅から2駅の立地です。
蔵本駅構内の路線図に記載されている駅で、アクセスしやすい四国八十八ヶ所霊場の札所は以下のとおりです。
板東駅/高徳線…1番札所霊山寺・2番札所極楽寺
板野駅/高徳線…3番札所金泉寺
府中駅/徳島線…16番札所観音寺・17番札所井戸寺
鴨島駅/徳島線…11番札所藤井寺
立江駅/牟岐線…19番札所立江寺
こちらの路線図には網羅されていませんが、牟岐線の羽ノ浦駅の先では以下の札所にアクセスできます。
新野駅/牟岐線…22番札所平等寺
日和佐駅/牟岐線…23番札所薬王寺
徳島県内の以上の四国八十八ヶ所の札所が鉄道の駅から近い立地です。
17番札所井戸寺を打ち終えたら、次の18番札所恩山寺まで距離約17.8km、そこに至る遍路道はいくつかありますが、どの道を経由してもある程度の距離があります。ゆえにこの区間は鉄道を利用して効率良く回るというお遍路さんが一定数存在することと思います。本記事でご紹介する蔵本駅を知らぬ間に乗り通しているお遍路さんもいらっしゃるかもしれません。なお、17番札所井戸寺の最寄り駅は府中(こう)駅で、18番札所恩山寺に近いといえる駅は中田(ちゅうでん)駅、どちらも難読駅名です。
蔵本駅

蔵本駅駅舎は、明治32年(1899)9月の開業以来の駅舎で、幾度かの改修を経て現在も使用されています。
全国的に諸所の問題から建て替えられて簡素化される駅が多い中で、戦前に建てられた駅舎や建造物が現役で使用される事例は年々減少の一途をたどっています。
蔵本駅の場合は終戦まで当地に陸軍司令部が置かれていたので敵機に狙われたことがあったでしょうし、隣の佐古駅は高架化されて古い鉄道痕跡が残っていないことを考えると、開業当時の遺構を数多く見ることができる蔵本駅の姿が奇跡的です。
古い駅舎が解体されバス停タイプの簡素な駅舎にリニューアルされた駅は、この路線図の中では府中駅と阿波赤石駅がそれに当たります。
※簡素な駅舎にリニューアルされた例として、香川県三豊市の讃岐財田駅を以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

蔵本駅が所属する路線は徳島線ですが、全国の単線非電化路線の中ではトップクラスの運転本数だと思われ、徳島駅と11番札所藤井寺がある鴨島駅までが徳島都市圏のような位置付けです。
徳島-鴨島は、JR四国路線の中で利用者数上位にランクインするほど、地元民の利用が多い区間です。時刻表の赤字は特急列車ですが、徳島駅と別格15番札所箸蔵寺に近い阿波池田の間を特急剣山が一日3往復運転していて、特急を含む全列車が蔵本駅に停車します。
蔵本は医学部を擁する徳島大学蔵本キャンパスがある学生の街で、鉄道が学生の通学と、病院利用者の通院需要に応えています。
ここに医学部が存在する点も、蔵本が歩んできた歴史そのものです。
長いプラットホームの理由

改札ラッチを通り抜けてプラットホームへ向かうと、その先に少し傾斜がある点が一つ要点です。
以前は写真の改札口で駅員が立ち改札や集札を行っていました。蔵本駅は平成6年(1994)頃に無人駅化されているため、現在は基本的に改札口での業務が行われておりません。

改札を通ってプラットホームに出て、西(鴨島方面)を眺めると、蔵本駅が非常に長いプラットホームを有していることがわかります。
戦前の蔵本には陸軍歩兵第43連隊が置かれ、軍需施設が立ち並んでいました。
蔵本駅南にあるむつみパーク蔵本(蔵本公園)や徳島大学蔵本キャンパスがある地点がかつて陸軍駐屯地があった場所で、現在の徳大医学部交差点付近に駐屯地の正門があったそうです。駐屯地に近い蔵本駅は、軍需物資輸送や兵員輸送の拠点として機能していたため、それが長大編成の列車であっても対応できなければいけません。長いプラットホームが設置されたのはそのためです。
蔵本の陸軍歩兵第43連隊から抽出された第三大隊は、昭和19年(1944)3月に当時日本の統治下にあったグアム島へ赴任します。そこで他部隊と共に島の防衛を担うことになりますが、着任間もない同年7月に米軍との間で勃発したグアムの戦いで、激戦の末玉砕してしまいました。同隊にとって結果的に蔵本駅が激戦地への旅立ちの駅になりました。
グアムの占領を成し遂げた米軍は飛行場を整備し、サイパン島などマリアナ諸島を日本本土への戦略爆撃の拠点とします。それらはこののち勃発したフィリピン・硫黄島・沖縄攻略において重要な役割を果たし、そこから飛び立ったB-29らによる戦略爆撃によって日本各地の都市は壊滅し、戦争の継続が困難になりました。皮肉にもその飛行場の前身は日本がグアム島を統治していた時代に造ったもので、自らが造成した飛行場が大戦の行方を決定づけることとなったわけです。
左の1番線が増床されて傾斜がある点は、次項で紹介します。
増床されているプラットホームの理由

この写真は、蔵本駅プラットホームの東端で、右が1番線、左が2番線、写真には写っていませんが、2番線プラットホームの反対側が3番線で、草ぼうぼうで使用されていないようですが、線路が残されています。
プラットホームの長さの次は、改修が加えられているプラットホームの事情について着目していきたいと思います。
現代の蔵本駅で列車が発着するのは、右の1番線が中心です。運転本数が多い時間帯に列車同士の行き違いや、特急列車を先行させるための退避線として、左の2番線が使用されている印象です。そのような運用がなければ、跨線橋を渡らなくて済む1番線かつ長大なプラットホームを歩き回らなくて良い駅舎改札付近に列車が停車します。なので多くの駅利用者にとって、写真のプラットホーム東端には用事が無いと思われます。
この写真の左の2番線をご覧ください。黒い部分は跨線橋の影ですが、そこの日向と日陰ではプラットホームの高さが異なることがわかります。

蔵本駅2・3番線のプラットホームは、大別すると3種類の資材が存在することがわかります。
下部から、
①自然石をコンクリートで固めて成型した低床プラットホームと斜めのコンクリートスロープ
=明治32年(1899)の駅開業時の元祖プラットホーム
②旧コンクリートスロープ上を右へ向かって増床された切石(自然石かコンクリートブロックかは不明)
=運用方法(主に軍需輸送)に応じて延長されたプラットホーム
③①の上部にコンクリートを流し込んで成形されたプラットホーム
=現代の運用方法に応じて増床されたプラットホーム
下部が斜めになっている部分があるので、ここが①当初のプラットホーム東端でしょうか。
その後、②利用状況によってプラットホームを延長、それほど長いプラットホームを必要としたのは、戦時対応ゆえかもしれません。
時は流れて、③昨今の車両運用に合わせるためにコンクリートで増床、蔵本駅が開業して今年で126年ですが、その運用の変遷をプラットホーム下部に見ることができます。
プラットホームの増床工事は、蔵本駅だけでなくこれまで全国各地で行われてきましたが、なぜ現代の車両が発着するためにプラットホームの増床工事を行わないといけないのか。
理由は現代の車両と昔の車両とでは地上からの高さが異なり、前者のほうが背高だからです。
問題が起きるのが乗降時で、旧式の低床プラットホームのままで現代の背高車両から乗り降りしようとすると、大きな段差が存在することとなり乗降に危険が伴います。

左が気動車(ディーゼル)、右が電車(モーター)で、電車は車高があることが分かり、更に屋根上へ電力を受けるためのパンタグラフが設置されるので、古い時代に建設された断面の小さいトンネルは架線を張ることができず、それを理由として電車を導入できない路線が全国各地に存在します。
どうして現代の車両が背高なのか。
現代の列車の動力はエンジンかモーターで、それらを車両に搭載していて自走できるものがほとんどです。昔の列車を思い浮かべてください。先頭に蒸気機関車がいて、後ろに客車が連なっている姿を想像できると思います。それが客車ではなく貨物車だったとしても同様です。客車や貨物車はエンジンやモーターを有しておらず自力で走ることができないため、それらを動かすためには動力機関を有する機関車に牽引してもらう必要がありました。
では現代の多くの車両が自走するための動力機関がどこに搭載されているのか。
それは車体下部になります。エンジン等によって発生した動力は車輪に伝えないといけないので、それは車輪の近くに置かなければいけません。なので動力機関の位置は車体下部で決まりです。ゆえに昔と今の車両を比較すると、現代の車両は下部に動力機関を搭載していて、その上に客室が設置されるのでどうしても背高になります。そしてそこから安全に乗降するためにプラットホームを増床することで、段差を可能な限り少なくしているわけです。
なお、鉄道発祥の地・ヨーロッパでは現代でも低床プラットホームが主流です。
日本にはないものとして欧州では他国との間で国際列車が多く運転されています。経済力のある国であれば車高に応じたプラットホームの更新ができるのでしょうが、財政が厳しい国ではそれが行えない場合があります。他国にそれを求めるわけにいかないので、低床プラットホームや乗降口(ドア)は低いままで客室内にステップ等を設けて対応しているケースが多いようですね。
ヨーロッパでも、都市部の地下鉄など営業範囲が限られたエリアだったり、相互乗り入れが無い鉄道事業者は、日本のように車両に合わせた高さのプラットホームで運用されているようです。
低床車両
〇空力特性
〇プラットホームの資材が少なくて済む
〇トンネルの断面が小さくて済む
▲車体下部の空間に制約があるので、高出力のモーターが搭載できない
背高車両
〇車体下部の空間に余裕があるので、高出力のモーターを搭載できる
▲走行時の空気抵抗が大きくなる
▲プラットホームを高く設けないといけない、または高く改修しなければならない
▲トンネルの断面を大きく取らなければいけない
※他にもメリット・デメリットがあります
日本のプラットホームの高さは100cm前後、ドイツ・フランス・ベルギー・イタリアで主流の高さは55cm、倍ほど違います。

跨線橋を渡って、先ほど居たプラットホーム東端の反対側になるプラットホーム西部分にやってきたのがこの写真で、右が2・3番線、左が1番線です。
ここでは2・3番線の半分だけ増床されているプラットホームがポイントです。3番線はレールこそ敷設されたままになっているものの、プラットフォームの増床は行われずホーム上の雑草もそのままです。その様子を見るに、3番線が使われなくなって相当時間が経過している気がします。
2番線に設置されているミラーは、発着する列車の運転士・車掌が後方確認を行うためのものです。この場所はすでにプラットホーム中央部から少し西へ離れた位置になりますが、現代でもこの付近までは列車の発着があるといえます。
それにしてもミラーからプラットホームの西端は、ご覧の通りまだだいぶ先です。その部分までフルに使用して列車が発着していた時代の、駅施設の賑わいは相当のものだったのではないでしょうか。
当時の風景を一目見てみたいと思いますが、探したり調べたりしても写真が全く見つからないあたり、軍事機密により蔵本駅周辺が厳重に秘匿されていたような気がします。
現在、蔵本には徳島大学蔵本キャンパスがあり、医学部や附属病院など大規模な医療施設が存在します。その起源は前述の医療施設が戦災に遭い、戦後この地に移転してきたことによるものです。かつての軍用地が今は徳島県内随一のメディカルゾーンに姿を変えています。
蔵本駅の日本最古かもしれない跨線橋

ここまでは主に蔵本駅の下の部分に目を向けてきましたが、次は蔵本駅の上に存在する部分に目を向けていきたいと思います。
写真の蔵本駅の跨線橋は明治時代建造の日本最古級の代物なのですが、その証となる部分を含め次記事でじっくり観察することにします。
※蔵本駅の跨線橋に関して、以下リンクの記事で紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【「蔵本駅」 地図】