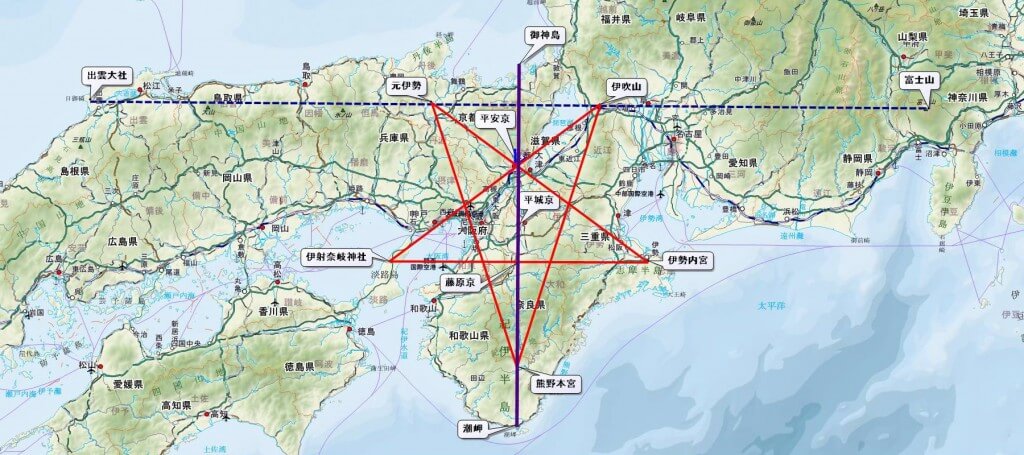徳島県徳島市の市街地に位置する「蔵本駅」では、明治期の鉄道遺構を見ることができます。日本最古かもしれない跨線橋の詳細部を見ていきたいと思います。

蔵本駅の1番線(右)と2・3番線(左)を繋ぐ跨線橋は、明治43年(1910)7月頃に設置された記載があり、原位置に立つ現役跨線橋としては、日本最古の可能性があります。
蔵本駅の概要や長いプラットホームを有していることを以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
日本最古級の跨線橋

跨線橋とは書いて字の如く「線路を跨ぐ橋」で、鉄道利用者が鉄道が往来する線路を渡ることなく安全に対岸へ渡ることができる設備のことをいい、道路であれば跨道橋(歩道橋)と呼びます。
パッと見て印象的なのは、床・壁共に板張りである点です。普段特に気を留めていない人でも、これだけで相当な古さを感じることができると思います。それだけだとあくまで抽象的な表現になりますが、跨線橋の入口にあたる左右下部の親柱に歴史の古さを表す確固たる記載があります。

親柱下部に「鐡道院」と記載されていて、これはJRの前身事業者の名称ですが、蔵本駅の歴史と合わせて時系列で見ていきたいと思います。
明治3年(1871年8月)
■工部省鉄道寮
↓
明治5年9月12日(1872年10月14日)
新橋-横浜間に日本初の鉄道が開業
↓
明治10年(1877)1月
■逓信省鉄道局
↓
明治32年(1899)2月16日
徳島鉄道・徳島-鴨島間が開業 ※当路線。私鉄としての開業
同年9月12日
蔵本駅が開業 ※当駅
↓
明治34年(1907)4月1日
■帝国鉄道庁
↓
明治40年(1907)9月1日
徳島鉄道を国有化(=帝国鉄道庁の管理下になった)
↓
明治41年(1908)12月4日
■内閣鉄道院
↓
明治43年(1910)7月頃
蔵本駅跨線橋設置
↓
大正9年(1920)5月15日
■鉄道省(省線)
↓
昭和24年(1949)6月1日
■日本国有鉄道(国鉄)
↓
昭和62年(1987)4月1日
■四国旅客鉄道株式会社(JR四国)
■は事業者・事業体の名称です
蔵本駅が現在所属するのはJR四国の徳島線ですが、蔵本駅は前身事業者の徳島鐡道が同路線を開業させてから約半年後に設置されました。駅舎はその時に建設されたものに改修を加えながら現在も使用されているようです。

跨線橋の親柱側面に「明治四十三年七月横河橋梁製作所」と記されていて、下部が埋没しているのは、後年プラットホームが増床されたためです。
明治43年は西暦1910年です。同年6月12日に岡山県の宇野港と香川県の高松港を結ぶ宇高連絡船(うこうれんらくせん)が開業、同航路は昭和63年(1988)4月の瀬戸大橋開業まで本州と四国を繋ぐ主要ルートであり続けました。宇高連絡船を介した本四連絡の形ができあがったことにより、この頃から四国の鉄道網が飛躍的に伸びていったことが想像できます。
横河橋梁製作所→現・株式会社横河ブリッジ
創業以来、鋼橋メーカーであり同分野では現在も国内最大手です。四国関連では明石海峡大橋、大鳴門橋、多々羅大橋などが同社による施工です。他では現在は跳開することはありませんが東京の勝鬨橋や、映画「戦場にかける橋」で知られるタイ王国のクウェー川鉄橋も同社の施工です。
同社は明治44年(1911)10月に鉄道院から橋桁製作工場に指定されていることから、「鉄橋」と呼ばれる橋の多くが横河橋梁製作所が手掛けたものといっても過言ではないほどです。事実、蔵本駅では耐荷重面では列車と比べると軽微な人道橋も手掛けているわけで、私は鉄橋を見ると製作事業者が記された銘板を探したくなります。

跨線橋を支える柱は鋳鉄製で、意匠に凝った四角柱の上に先が細くなる円柱が伸びる形状、これは明治後半から大正にかけて盛んになった洋風建築を取り入れた表現方法で、全国各地で広く目にすることができます。
それまでアメリカやイギリスからの輸入に頼っていた鋼材を、国内で賄うことができるよう政府主導で建設されたのが、官営八幡製鉄所(現・日本製鉄九州製鉄所)で、明治34年(1901)の出来事です。
とはいえ国内製造だけで鋼材の需要を賄うことができるようになったのはそれよりまだまだ先のことで、開業時点では地方のいち私鉄事業者が、レール以外の部分に貴重な鉄を使用することは難しかったでしょうね。
※明治時代後期に全ての鋼材をアメリカ合衆国から輸入して架橋された東洋一と謳われた鉄橋について、以下リンクの別サイトの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
かつて東洋一と歌われた名鉄橋の今「余部橋りょう/兵庫県香美町」
日本最古の跨線橋

本記事のタイトルで蔵本駅跨線橋を日本最古「かもしれない」としたのは、日本最古を名乗る跨線橋が全国にいくつかあるためです。
個人的には蔵本駅の跨線橋が日本最古だと思っているのですが、同カテゴリーに名乗り出る跨線橋を挙げて比較してみます。

「I.G.R. MAKERS KOBE 1890」の刻印を見ることができる島根県大田市駅跨線橋は、原位置は不明であるものの、移設されて供用されている跨線橋では日本最古とされていて、I.G.R.は「Imperial Government Railway」のそれぞれ頭文字で、JRの前身組織である帝国鉄道庁の英語略称です。
【明治23年/1890、大田市駅(島根県)】
日本最古の跨線橋は島根県大田市の大田市(おおだし)駅にある跨線橋で、明治23年(1890)製造のものです。日本国内で最古と言われている跨線橋は、蔵本駅がそうであるように明治40年代製造のものがいくつか存在しています。それからいくと明治20年代の大田市の跨線橋はぶっちぎりの古さです。ただし石見大田駅(現・大田市駅)の開業が大正4年(1915)7月なので、こちらはどこからか移設されたものと考えることができます。
【明治40年/1907、八鹿駅(兵庫県)】
大田市駅と同じ山陰本線では八鹿(ようか)駅の跨線橋が明治40年(1907)の建造ですが、こちらは昭和30年(1955)に福知山駅から移設されたことが記録されているので、大田市駅と同じく原位置ではありません。
【明治43年/1910、半田駅(愛知県)】
これまで原位置にある最古の跨線橋といわれていたのが、愛知県半田市の半田駅の跨線橋です。当サイトの記事にも度々登場している、知多四国八十八ヶ所霊場の18番札所光照寺や19番札所光照院の近くにあるJR武豊線(たけとよせん)の駅にあったものです。跨線橋の設置は明治43年(1910)11月の記録が残り、原位置にある跨線橋として長らく最古といわれてきました。近年、JR武豊線半田駅付近連続立体交差事業により令和3年(2021)6月に供用停止になり、新しい駅周辺に整備される公園に跨線橋が移設されるようです。
【明治44年/1911、鶴田駅(栃木県)】
半田駅の跨線橋が供用停止後に原位置で最も古い跨線橋になったといわれるのが、栃木県宇都宮市の鶴田駅にある跨線橋で、明治44年(1911)の建造です。こちらは平成20年(2008)年に、近代化産業遺産に指定されています。
【明治43年/1910、蔵本駅(徳島県)】
そして蔵本駅の跨線橋が明治43年(1910)7月と跨線橋に記されています。おそらく設置以来場所は変わっていない「原位置に立つ跨線橋」と思われます。それでいくと、大田市駅の跨線橋はともかく、そもそもが半田駅にあったものより古いと思うのですが「最古の跨線橋」との記載がどこにも見当たりません。
・横河橋梁製作所で鋳造されたのがその年月で、蔵本駅に設置されたのが後年だった?
・跨線橋の要件を満たしていない?
「原位置に立つ跨線橋」とは「初めからその場所に立っていて移動していない、かつ現役の跨線橋」という意味です。蔵本駅の跨線橋が最古の話題にランクインしない理由がわからないのですが、古いことは間違いなさそうなので次代にも残って欲しいと願います。
跨線橋内部

板の取り換えや再塗装、ゴムステップや手すりの設置はあれど、多くの部分が設置当時のものと思われる蔵本駅の跨線橋内部です。
日本最古の跨線橋を渡らせてもらいます。
木製の階段踏板や羽目板壁に古さを感じます。子どもの頃、小学校にあった木造校舎を彷彿させる雰囲気があり、どこか懐かしさが感じられます。叶うならば昔と今の写真を並べて見てみたいですね。残念ながら蔵本駅が軍事施設と近かったゆえか、インターネットで検索しても昔の跨線橋の写真が出てきません。

跨線橋の階段を上がってきて、窓から南側を眺めると、大学病院やその後ろに眉山が見えます。
蔵本駅周辺に軍事施設があったわりには、窓の高さは標準的で、昔の日本人の体格に合わせた位置です。善通寺駅のように外が見えず明り取りに特化しているような感じはないです。もっとも戦時中は窓が暗幕で覆われていたでしょうし、跨線橋上で立ち止まって外を眺めようものなら、憲兵さんがすっ飛んできたでしょうね。おそらく渡ることだけが許されていたことでしょう。こうして跨線橋を記事にできるのも、平和な時代だからこそです。
※駅舎が現存日本最古の可能性がある善通寺駅の跨線橋を以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

手前が南側(1番線)で奥が北側(2・3番線)の跨線橋の渡り部分です。
ここでのポイントは渡り部分の床板は木製ではなく、アスファルト舗装になっていることです。万が一床板が破損していて、人や物が線路に落下するのを防ぐ観点でしょうか。善通寺駅の跨線橋も渡り部分はアスファルトだった気がします。
目を上に向けると、跨線橋の骨格となる鋼材同士がリベット(鋲)が加締められています。一般的な鉄橋を思い浮かべてください。アーチの鋼材(橋上の鋼材)があって、それを補強するトラス(斜めの鋼材)や橋桁(横の鋼材)が丸い金具で接合されていますが、その丸い金具がリベットで、さすが鉄橋メーカーが製造した跨線橋というところです。
リベットに代わる技術として溶接という手法がありますが、日本における溶接の歴史は意外と浅く、大正3年(1914)に三菱長崎造船所に導入されたのが始まりとされます。すなわち蔵本駅の跨線橋が建設された当時は溶接技術が伝わっていないか未発達だったため、鋼材の接合はリベットが用いられたと考えることができます。リベット接合だと重量増とそれを加締める手間がかかります。溶接でも手間は必要ですが、資材の節約と軽量化を図ることが可能です。
※無数のリベットを加締めて結合されている鉄橋の例(ここではリベットをピンと呼んでいますがほぼ同じものです)を以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
跨線橋上から見える景色

跨線橋上から東(徳島方面)を眺めていると、列車がやって来ました。
やってきた列車は阿波池田行きの各駅停車です。明治時代に敷設された線路に、平成時代に製造された列車が走ります。

跨線橋上から西(阿波池田方面)を眺めると、阿波池田へ向かって長いプラットホーム横を列車が加速していきました。
徳島県内で列車撮影を行う魅力の一つに「架線が存在しない」ことが挙げられます。
徳島県は47都道府県で唯一「電車が走ったことが無い」県です。景色や鉄道を眺めるのが好きな者にとっては、架線が無い分列車がすっきり見えるのと、空が広く映るのが良いと思っています。電線が地中化された市街地の上空がすっきりしているのと同じ感じですね。
蔵本駅の長いプラットホームを俯瞰するのも魅力的ですが、徳島県の中心駅である徳島駅やこちらの列車の行先である阿波池田駅は、広大な敷地に何線もレールが敷設された徳島県における鉄道ターミナル駅で、そこで行き交う列車を眺めるのもお勧めです。
これまで徳島県で電車が走る可能性が無かったわけではなく、明治45年(1912)11月に阿波電気軌道という会社が電車として敷設免許が下りています。同社は発電所の事情や資金繰りの関係で暫定的に気動車(=エンジン)で運行が開始され、結果的に電車運行が実現されることなく国有化されました。それ以降は徳島県内で電鉄会社を設立する動きは聞かれません。現在の鳴門線や高徳線(一部)の前身が、電車運行を目指して鉄道を敷設した阿波電気軌道の路線になります。
※蔵本駅前にある「蔵清水」に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【「蔵本駅」 地図】