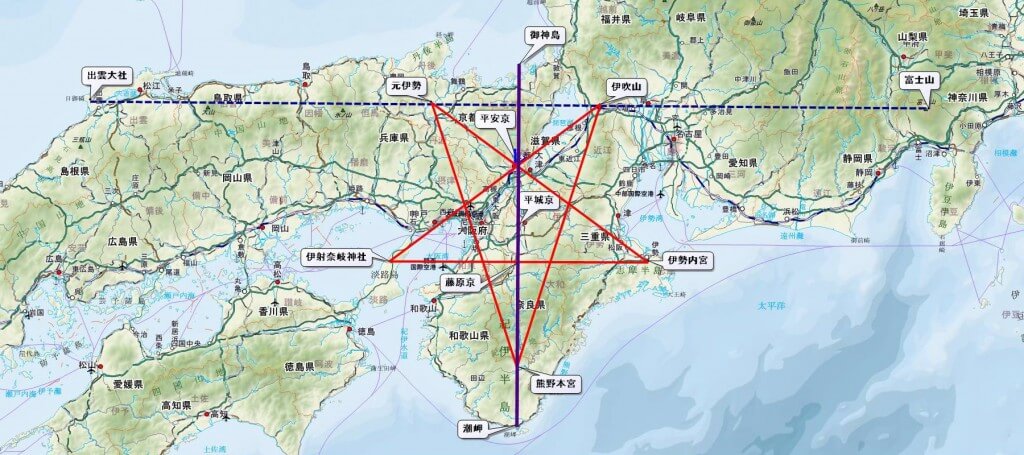戦前は軍都だった徳島県徳島市蔵本町、蔵本駅を通じて幾多の兵士がここから戦地へと旅立っていきました。戦争に伴って造成された広場には現在は「蔵清水」が湧出しています。

かつて存在した民家が持っていた暮らし水が「蔵清水」となって現代に継承されています。
※蔵本駅に関しては、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
軍用地から医療施設へ様変わりした蔵本

蔵本駅は駅出入口があるのは南側だけで、そこが楕円形のロータリーになっています。
蔵清水がある場所が駅前広場のほぼ中心で、そこを境に西側(写真右)がコインパーキング、東側(写真右)が契約駐車場になっています(植栽の左。写真には映っていません)。
蔵本駅前のこの場所は昭和の初め頃までは住宅地で、駅前には民家が立ち並んでいました。それが昭和14年(1939)に蔵本駅前に出征兵士の整列場所を作ることになり、軍部の命令により民家12軒が立ち退きを命じられ広場に変わりました。それぞれの家庭には井戸があり、それがすなわち「暮らし水」。家々は撤去されて広場になってからも、現在とは異なる形で湧水が存在したようです。

蔵清水がある場所(広場ほぼ中央)から南に向かって伸びる道の方向を見ると眉山(びざん)があり、道の先および眉山のふもとに見えているガラス窓の建造物が徳島大学医学部です。
現在、徳島大学医学部がある場所が終戦まで陸軍歩兵第43連隊の駐屯地でした。この道と国道192号との交点である徳大医学部前交差点が、かつて駐屯地の正門があった地点です。
当時は兵士が出征する際には沿道に大勢の市民が集まり、国旗を振って国の命運を託したことでしょう。出征だけでなく、任務を終えて帰還した兵士も市民の歓声に迎えられてこの道を歩いたことと思います。
戦後、軍用地は徳島大学医学部を中心とする医療施設に転用されて、徳島県随一のメディカルゾーンになりました。蔵本は学生の街であり、医療を享受する人々にとってはなくてはならない場所になっています。
現代に継承された「蔵清水」

家庭の暮らし水から戦争を経過した後、平成3年(1991)に蔵本自治会によって給水設備とモニュメントが整備されました。
通常の湧水は山地から湧き出ていたりするものがイメージされますが、蔵本町は医療施設や民家が立ち並ぶ市街地です。ロケーションだけでいえば水が湧き出ている場所なのが不思議に感じられます。そんな市街地真っ只中に、このような清らかな水が湧き出ているのはとても貴重ですね。
そこはやはり市民にとても親しまれている湧水のようで、蔵本駅の写真を撮っている間にも、大小様々な容器を携えた人がひっきりなしに訪れては、蔵清水を容器に納めているのを何度も目にしました。

蔵清水は常時湧き出ているわけではなく、センサーに手を当てると一定時間湧水が供給される仕組みです。
湧出量は多く、私が訪れた時は持参していた4リットルペットボトルがものの1分もしないうちに満タンになりました。湧出口が二つあるので複数の人と給水のタイミングが重なっても、ある程度は円滑に順番がやってきそうです。
蔵清水の案内には水質検査の値などが掲出されていますが、ご利用は各人のご判断にてお願いします。
また自家用車で訪れた場合は、蔵清水西側にあるコインパーキングを利用することになると思いますが、その代金は蔵清水の維持管理費に当てられているようです。
遍路道に面しているわけではないので、お遍路さんが水を汲みに訪れるという場所ではあまりないように思いますが、広義的な意味での17番札所井戸寺から18番札所恩山寺への道中にある史跡および給水ポイントとして、紹介させていただきました。
【「蔵本駅 蔵清水」 地図】