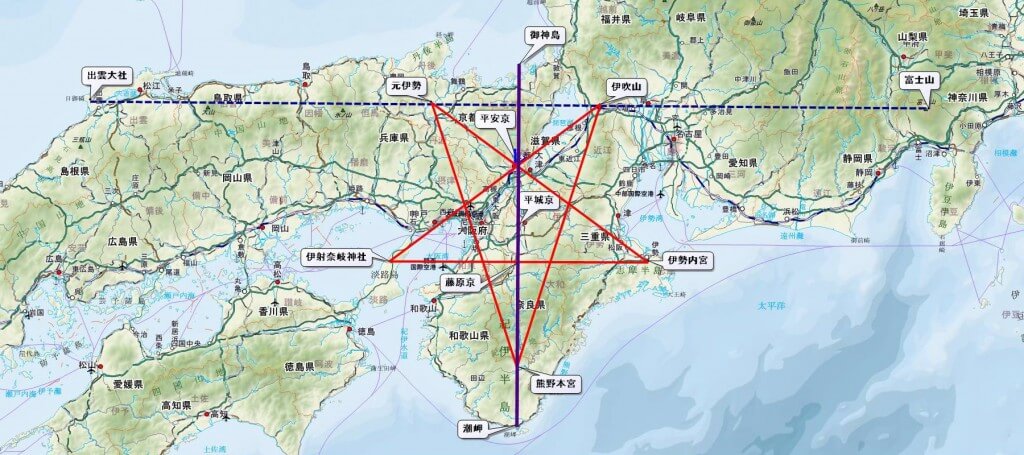土佐の小京都・中村の玄関口に、中務茂兵衛標石が残されています。このエリアでは四万十川の渡って38番札所金剛福寺がある足摺方面に向かわなければいけませんが、当時の遍路ルートも現代と同様に複数の選択肢があったと思われます。

国道56号沿い、古津賀駅前
中務茂兵衛 < 弘化2年(1845)4月30日 - 大正11年(1922)2月14日 >
周防國大嶋郡椋野村(現 山口県周防大島町)出身。
18歳の頃に周防大島を出奔。明治から大正にかけて 一度も故郷に戻ることなく、四国八十八ヶ所を繰り返し巡拝する事 279回。バスや自家用車が普及している時代ではないので、殆どが徒歩。 巡拝回数は 歩き遍路最多記録 と名高く、また今後も上回ることはほぼ不可能な不滅の功績とも呼ばれる。
明治19年(1886)、茂兵衛42歳。88度目の巡拝の頃から標石の建立を始めた。標石は四国各地で確認されているだけで243基。札所の境内、遍路道沿いに多く残されている。
—– こちらの記事に登場する主な地名・単語
標石(しるべいし)
周防國大島郡椋野村(すおうこくおおしまぐんむくのむら)
第38番金剛福寺(だい38ばんこんごうふくじ)
足摺(あしずり)
四万十市(しまんとし)
中村(なかむら)
渡川(わたりがわ)
四万十川(しまんとがわ)
分限者(ぶげんしゃ)
※これまでに調査した中務茂兵衛の標石に関して、以下リンクの記事に一覧でまとめていますので、こちらもぜひご覧ください。
標石の正面に表記されている内容は

足摺と刻字されている
左(指)
三十八番足摺山
備前國岡山片瀬町
施主倉田万造
刻字を完璧に読み取ることができる、保存状態の良い標石。
この場所は四万十市の入口にあたり、横を通る国道56号はかつての中村街道。現在、遍路地図に記載されている遍路道は、この場所は通りません。道の駅ビオス大方付近から海沿いを進んで四万十川河口の渡し舟か(※不定期運航)、現在はそれより少し内陸の道を進んで四万十大橋を渡って足摺を目指します。
※渡し舟、四万十川を渡ったあとの遍路道に関しては、以下リンクの記事でご紹介しています。
【37番札所岩本寺→38番札所金剛福寺】四万十川最後の渡しは今も細々続いているようです
【37番札所岩本寺→38番札所金剛福寺】四万十川渡し場分岐に残された中務茂兵衛標石
ではなぜこの場所に標石が?
考えられるのは、中村街道は比較的早い時代から整備された土佐の往還道であり、進度を計算できる道は標石建立当時この道だけだったのかもしれません。海沿いの道は繋がっていなかったか、地図に記載されていなかったか。
また、四万十川河口まで到達したところで、そこの渡船は太平洋に面しているため天候に左右され易い。当時渡川(四万十川)を渡る手段は、河口・中村市街共に渡船ですが、河口から少し上流に位置する中村城下で川を渡った方が利便性が高かったのかもしれません。
また「足を摺るほど断崖絶壁が続く」ことが地名の由来になった足摺方面へ進むにあたり、食糧の確保など準備のため中村市街に立ち寄ることがセオリーだったとも考えることができます。

岡山の施主によるもの
備前國岡山片瀬町
高知城近くで見られる標石でも見られた「岡山片瀬町」。施主さんもそれと同じ「倉田万造」さんです。
※高知城近くの標石に関しては、以下リンクの記事でご紹介しています。
【30番札所奥の院安楽寺近く】高知城近くにある標石から読み取る当時の四国遍路界
岡山市内を流れる旭川沿いに位置する片瀬町(現岡山市北区京橋町付近)は、かつて四国へ渡る定期船が出港していた場所。街は港町として賑わったことが想像できますが、この時代に標石を複数寄進するくらいの人物なので、地域の分限者かもしれません。
標石の右面に表記されている内容は

中村の刻字
右
中村(※右から)
臺百四十九度目為供養
周防國大島郡椋野村
願主中務茂兵衛義教
中村城下への方角が記されています。
標石が立つ四万十市古津賀は市中心部への入口にあたるのは、今も昔も同じ。この場所が中村市街と次の札所である足摺方面への分かれ又ゆえ、標石が必要だったのでしょう。元々は現在の位置とは少し違う場所にたっていたと思われますが、道路拡幅工事により、安全な歩道部分へ移されたものと察します。
中務茂兵衛、149度目の四国遍路は52歳の時のことです。
標石の左面に表記されている内容は

世界ではオリンピックが初めて開かれた年
明治29年四月吉辰
西暦では1896年。
同年同月、ギリシアのアテネで第一回オリンピックが開催されました。
【「古津賀駅前の中務茂兵衛」 地図】