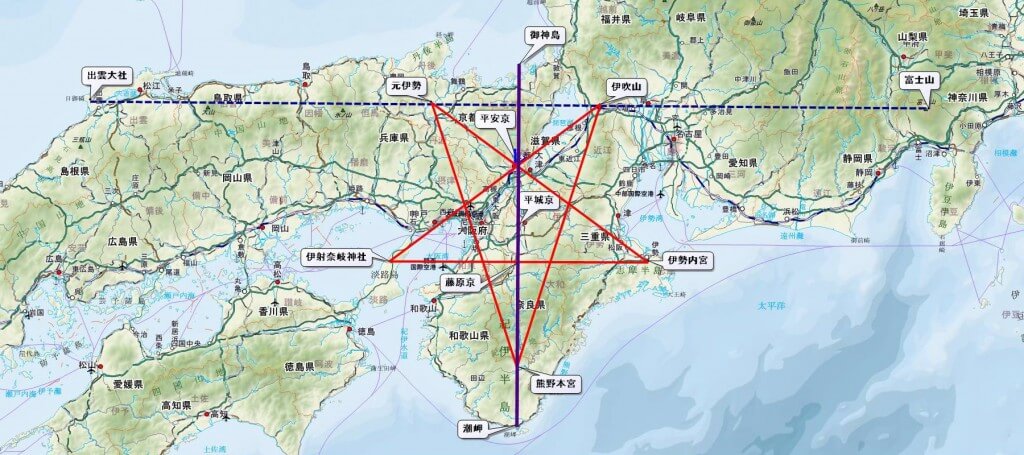江戸時代の四国の街道は「全ての道は金毘羅に通ずる」とまでいわれ、金刀比羅宮を目指す道が主要道でした。明治時代が過ぎ大正時代になっても、分岐地点を変えて街道が健在だったことを表す標石が金刀比羅宮近くにのこされています。

四国新道が開通後の大正時代に、金刀比羅宮の南にある三叉路が四国各地との接点だったようで、古い標石がのこっています。
標石が立っている場所

三叉路のわかれ又に立って北側を向くと、道路はここから左(西)右(南)にわかれています。
奥が金刀比羅宮(こんぴらさん)方面で、林がある地点には重要文化財の鞘橋(さやばし)があります。この場所は観光で訪れるような場所ではありません。
※金刀比羅宮に関して、以下リンクのオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。
【御朱印情報】香川県「金刀比羅宮(こんぴらさん)」の本宮と奥社で授与されるアート御朱印
標石の正面に表記されている内容

右の方角は西なので、愛媛県や香川県西部の観音寺に行く場合はこちらを右に曲がります。
<正面>
右
いよわだはま
くわをんじ
いよ→伊予 現・愛媛県
わだはま→和田浜 現・香川県観音寺市豊浜町和田浜
くわをんじ→観音寺(かんおんじ)
当面のポイントは「和田浜」ですね。他の面に記載されている地名と比べてもマイナーな存在ですが、香川県西部のかつて伊予土佐街道と丸亀街道が分岐していた場所です。和田浜から丸亀に行くのであれば北東に行くほうが近いですし、金刀比羅宮や高松に向かうのであれば東北東へ行くほうが近い、その分岐点が和田浜でした。現代に国道11号・国道377号の姫浜交差点として踏襲されています。
和田地区は第68・69代内閣総理大臣を歴任した大平正芳(おおひらまさよし/1910-1980)氏の出身地でもあります。
※和田浜の地名は、以下リンクの記事でご紹介している中務茂兵衛標石にも記載されていますので、こちらもぜひご覧ください。
【65番札所三角寺→66番札所雲辺寺】土佐國まで続く旧土佐街道沿いの中務茂兵衛標石
標石の左面に表記されている内容

こちらを左面と同定しましたが、内容的にはこちらが正面といっても遜色がなく、正面2面と裏面1面のような構成の標石です。
<左面>
左
とさあは
はしくら
とさ→土佐 現・高知県
あは→阿波 現・徳島県
はしくら→箸蔵 別格15番札所箸蔵寺
当面のポイントは「土佐」が「阿波」と一緒に併記されている点です。
明治時代以前の土佐街道は川之江(現・四国中央市)まで伊豫街道と重複していて、重複区間は伊豫土佐街道と呼ばれていました。なのでこちらの石が明治時代初期やそれ以前のものであれば、正面の「いよ」となっているところが「いよとさ」になると思います。
土佐の重複相手が阿波に代わったのは明治時代中期のことで、新しく建設された道に由来します。
「あはとさ」の方向へ少し行ったところにある香川県境の街・三豊郡財田上村(みとよぐんさいたかみむら、現・香川県三豊市財田町)出身の大久保諶之丞(おおくぼじんのじょう、1849-1891)という政治家がいました。四国各県を結ぶ幹線道路の必要性を提唱した人物です。その道路は「四国新道(しこくしんみち)」の名で着工され、丸亀から阿波池田を経由して高知へ、高知から佐川を経て松山へとつながりました。
多度津
│
金蔵寺---丸亀
│
琴平
│
池田
│
高知
│
佐川---須崎
│
松山
香川と高知(概ね現在の国道32号に相当)
高知と松山(概ね現在の国道33号に相当)
という四国内の都市間連絡道路の起源は、この時に建設されたものに遡ります。起点が高松ではなく丸亀なのもポイントです。
四国新道の着工は明治17年(1884)、完成は明治27年(1894)。着工時点では香川県が世に存在していなかったので高松の地位が低かったことと、大久保諶之丞は明治22年(1889)時点で瀬戸大橋の構想を発表するくらい人物だったので、そことの接続を考えていた部分があったのかもしれません。瀬戸大橋が完成したのはそれから約100年後の昭和63年(1988)です。
土佐と阿波が併記されているのは、既に四国新道が完成していた証と見ることができそうです。
※四国新道完成以前の土佐街道上に建てられた中務茂兵衛標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【65番札所三角寺→66番札所雲辺寺】土佐街道を越えて来た旅人のための中務茂兵衛標石
「はしくら」を漢字表記すると「箸蔵」となり、別格15番札所箸蔵寺がある地域をさします。箸蔵寺は「こんぴら奥之院」と呼ばれ、金毘羅大権現だけでは片参りになるからと、金毘羅と箸蔵の両こんぴら参りが奨励されていました。その存在感は愛媛県東部から香川県西部の標石には、たびたび「はしくら」の行先が登場する点にみることができます。「あはとさ」の方向へ、箸蔵詣りの人たちが向かったんじゃないかなあと想像します。
※財田地域の箸蔵寺へ向かう登山口となる地点にのこされている標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【香川県三豊市財田町】箸蔵寺を参拝した巡礼者が手がかりにしたと考えられる標石
標石の右面に表記されている内容

この標石が建てられた頃、世界的なパンデミックとして恐れられたスペイン風邪が流行していました。
<右面>
大正八年六月●
大正8年は西暦1919年。同年同月28日、ドイツが連合国とヴェルサイユ条約を締結し、第一次世界大戦が終結しました。
この時期の日本を含む世界はスペイン風邪が流行して戦争どころではなくなり、それが理由で第一次世界大戦が終結したという見方もあるほどです。日本は欧米から遅れて流行する傾向があったようで、標石が建てられた時期は第一波の収束頃にあたり、欧米では第三波の収束前で、それが結果的に最後の流行の波になりました。日本はここから二波三波がきて、収束は大正10年(1921)7月頃だったようです。
現代の街道分岐点

仲多度郡まんのう町買田東交差点の分岐を示す道路標識をみると、現代ではこの場所から四国各方向へわかれていくことがわかります。
後年にバイパスが整備され、四国各県へのクロスポイントとしての機能は写真の道路標識が示す交差点に移りました。
東(国道32号)…高松
西(国道377号)…香川県西部、愛媛県
南(国道32号)…徳島県西部、高知県
北(国道319号)…琴平、多度津、丸亀、本州
大久保諶之丞が提唱した四国新道は、この付近は北から南(写真では右から左)へ縦貫していました。大正時代の丸亀・多度津には本四連絡船が発着していたので、北の方角は本州(岡山)と繋がっている道という見方もできそうです。
※大久保諶之丞に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【琴平公園】明治時代に四国の道路整備を行った「大久保諶之丞」の銅像
※琴平町内にある鉄道遺構に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【香川県琴平町】金刀比羅宮行き鉄道4社の「こんぴら鉄道競争」の痕跡である鉄道立体交差
【香川県琴平町】川の中にのこる「こんぴら鉄道競争」の痕跡である琴急橋脚跡
【「大正時代の金毘羅街道合流地点にのこる標石」 地図】