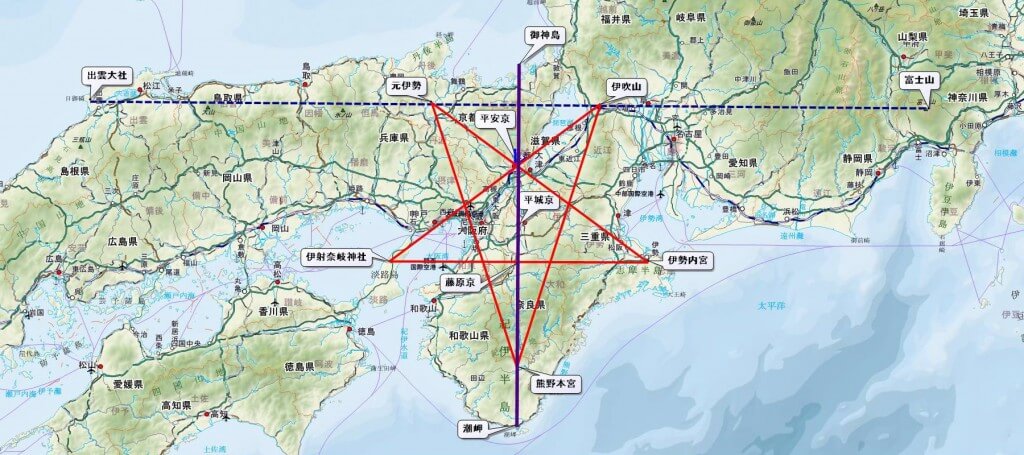戦前の一時期に金刀比羅宮に向かう鉄道4社が乗り入れていた琴平町には複数の鉄道遺構がのこっています。金倉川の中に、かつて琴平急行電鉄が通っていた橋の橋脚跡をみることができます。

琴平に乗り入れていた鉄道4社のうち、現存している2社のうちの1つが高松琴平電気鉄道で、終点琴電琴平駅の横には、かつての金毘羅詣のシンボルともいえる高燈篭がそびえます。
※琴平町内にある鉄道遺構の鉄道立体交差と、鉄道4社の変遷に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
【香川県琴平町】金刀比羅宮行き鉄道4社の「こんぴら鉄道競争」の痕跡である鉄道立体交差
琴電琴平駅と高燈篭

琴電琴平駅の位置は開業時から変わっておらず、駅に最接近できる西側の車道から撮影しました。
高松琴平電気鉄道(ことでん)で琴平へやってくると、背の高い松並木と高燈篭がお出迎えしてくれます。このストーリーがとても良いですね。
琴電琴平駅の横にある高燈篭の高さ27mは木造燈篭としては日本一を誇ります。完成は江戸時代の万延元年(1860)で、昔は丸亀の港に真っ暗な夜に上陸したとしてもこの高燈篭が煌々と光を放つ様が見えて、その光を拠り所に金刀比羅宮(ことひらぐう、こんぴらさんの愛称で親しまれている)へやってきたといわれています。
※金刀比羅宮に関して、以下リンクのオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。
【御朱印情報】香川県「金刀比羅宮(こんぴらさん)」の本宮と奥社で授与されるアート御朱印
琴平に乗り入れるもう1つの現存鉄道事業者、JRの琴平駅と琴電琴平駅は200mほど離れた場所にあり、徒歩での乗り換えが可能です。今回はJR琴平駅方面には行かず、琴電琴平駅西側の道路を少し下流方向へ進みます。
省線→現JR ※現存
琴平電鉄→高松琴平電鉄(ことでん) ※現存
琴平参宮電鉄(琴参)→戦後廃止
琴平急行電鉄(琴急)→戦中廃止
満濃池から流れる「金倉川」の名称に関するあれこれ

琴電琴平駅と金倉川に挟まれた道路を下流方向にやってくると、この道沿いには、琴電琴平駅を利用する人向けのパーク&ライド用駐車場及び駐輪場があり、写真の自動車が停まっている地点がそれにあたります。
流れている川の名前は「金倉川(かなくらがわ)」で、上流へ向かうと満濃池があります。すなわち、四国八十八ヶ所霊場と別格二十霊場を一緒に回っているお遍路さんは、理論上はこの川に沿って上流方向に向かえば大師遺跡の満濃池や別格17番札所神野寺に行くことができます。川沿いにずっと道があるわけではありませんが、JRにしろことでんにしろ、徒歩で満濃池へ行く際は琴平駅が起点と考えても良いかもしれません。
一方、下流へ向かうと丸亀市中津町付近で瀬戸内海に流れ出ます。
川の名前…金倉川(かなくらがわ)
寺の名前…76番札所金倉寺(こんぞうじ)
字名…金蔵寺町(こんぞうじちょう)
駅名…金蔵寺駅(こんぞうじえき)
日本語の難しいところですね。同じ字でも読みが違ったり、異なる字でも読みが一緒だったり。
このように複雑になったのは、川や寺の名前は周辺の古い地名「金倉郷(かなくらごう)」に由来するようで、金倉郷の●●という感じです。
字名(あざな)については金倉郷が由来なのは同じなのでしょうが、
倉…穀物を貯蔵する倉庫
蔵…穀物貯蔵だけでなく家財も保管する倉庫
地名となるとそこは人が生活する場所なので、倉をより相応しい蔵の字に変えたという風に聞いたことがあります。郷にとって金に等しいものは米でしょうし、家にとっての金は金銀財宝でしょうから、地名の発展的変化ですね。後年に鉄道が敷設された際には金蔵寺町にある駅だから金蔵寺駅となったようです。
金倉川の中にのこる琴平急行電鉄の「橋脚跡」

琴電琴平駅の横道に沿って金倉川を下流に進むと、ある地点で川の両岸近くに楕円形のコンクリート構造物を確認することができます。
上の写真のコンクリート構造物は、橋脚の基礎部分です。かつてこの場所に鉄道橋が架かっていました。失われた鉄道のうち、琴平参宮電鉄はこの場所では金倉川を渡らないので、琴平急行電鉄のものになります。

護岸工事によって橋台など陸上の構造物は失われていますが、健在である橋脚の基礎を頼りに鉄橋が掛かっていた様子を想像してみます。
道路にしろ線路にしろ、川に橋を架ける時は通常は川の流れに対して直角に架橋します。斜めにしてしまうと、橋桁の延長が増大するので、資材がその分多く必要になるためです。大水時の水の抵抗が不均等になるデメリットもあります。
けれど、こちらの橋脚跡を見る限り金倉川に対して斜めに架橋されていたようです。ちなみに琴急の駅は写真では中央の白いビルの右側、現在の琴平郵便局付近にあったようです。
ここで考えるのが、斜めの橋を架けてまであの位置まで鉄道を敷設した点です。4社の琴平駅立地から考察したいと思います。
省線(現JR)→4社の中で参道口まで一番遠い。もっとも初代地から現在地への移転が高知県への延伸を図ってのことなので、こんぴら輸送だけを意識していなかったと思われる。
ことでん→金倉川右岸にあり省線に次いで遠く、昔の立地も現在地と同じ。高松からの輸送面でのライバルは省線なので、それより距離・速さ・運転頻度で勝り、参道口まで近いため目的は達成していたのかもしれない。
琴参→省線の初代琴平駅の跡地に設置され、参道口に最も近かった。金倉川の左岸を走ってくるため橋を架ける必要が無かった。
琴急→最後発なのでめぼしい場所は他3社におさえられていた。経路におけるライバルは琴参で、遅れを取るわけにいかない。斜めの橋を架けてでも可能な限り参道口に近い位置に駅を設置した。
琴急は良くいえば相当がんばったということになりますが、かなり無理をしていた様子がうかがえます。発着地を同じとする琴参を意識していたことがみえてきます。
琴平急行電鉄は社名に「急行」と付いていますが、全列車が各駅停車で運転されていました。戦前は既存の鉄道があって後発の鉄道事業者が誕生する際、先発の鉄道より早く目的地に到着できますよ、ということをアピールしたかった場合に付けられた例が多いです。
東京急行(東急)
京浜急行(京急)
小田原急行(小田急)
京阪神急行(阪急)
など、急行を冠する鉄道事業者は大手私鉄ばかりですね。
琴急が路線が競合していた他社と比べて急行だった部分に触れておきたいと思います。
【路線距離/坂出-琴平】
琴急:15.7km
琴参:20.6km ※丸亀経由のため
省線:22.3km ※多度津経由のため
【所要時間/坂出-琴平/昭和16年】
琴急:36分
琴参:1時間3分
省線:37~43分
【運転頻度】
琴急:30分間隔
琴参:20分間隔
省線:18往復 ※おおむね1時間に1本
琴参は軌道区間(路面電車)を多く含み、省線は汽車での運転だったことから、電車で専用設計の琴急が急行だったことは確かなようです。
しかしながら戦争の激化によって昭和19年(1944)1月に不要不急線に指定され各種設備を供出、昭和23年(1948)7月にはライバルだった琴参に吸収されますが、旧琴急の路線が復活されることはなく昭和29年(1954)9月に正式に廃止になりました。
新しく親会社になった琴参も昭和38年(1963)9月に鉄道事業を廃止し、バス専業になり現在に至ります。
結果的に参道口に近い位置にターミナルを持っていた2社が廃止になり、遠い位置にターミナルを設けた2社が現存している点も興味深いですね。
【「琴急橋脚跡」 地図】