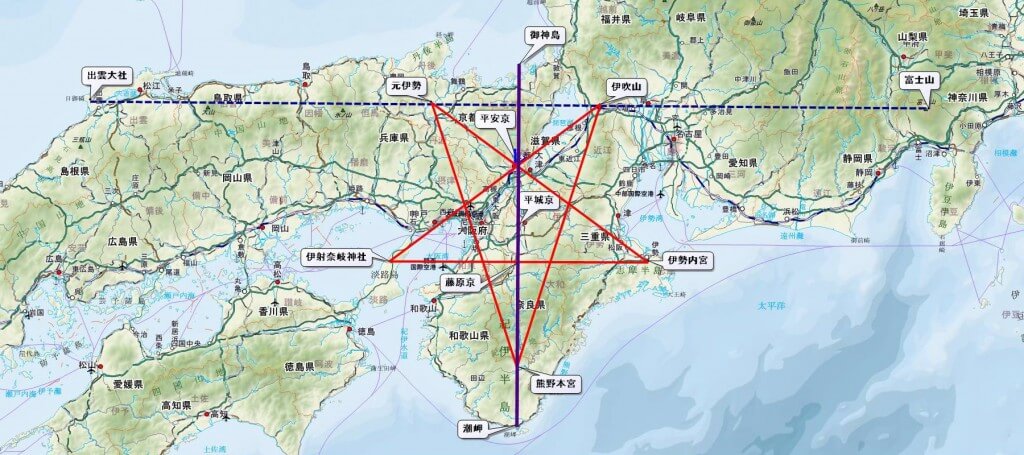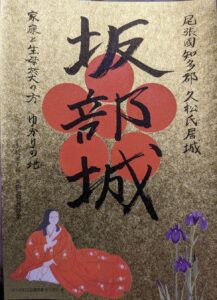知多四国霊場87番札所長寿寺周辺の地域は、戦国時代に織田信長と今川義元が戦った「桶狭間の戦い」の舞台になりました。激戦の歴史を現代に伝える「鷲津砦跡」と「丸根砦跡」が国の史跡に指定されのこされています。
「桶狭間の戦い」の舞台
愛知県名古屋市緑区の大高町から豊明市にかけての地域は、戦国時代の永禄3年5月19日(1560年6月12日)に、織田信長(おだのぶなが)の軍と今川義元(いまがわよしもと)の軍が戦った「桶狭間の戦い(おけはざまのたたかい)」の舞台として知られています。
桶狭間の戦いは、織田信長が今川義元の大軍を奇襲し、勝利を収めた戦いです。この勝利により、織田信長は戦国大名としての地位を確立し、天下統一に向けて大きく前進しました。
この戦は、戦略の革新を象徴する出来事となり、今川家の衰退やのちに江戸幕府を開く徳川家康(とくがわいえやす)の台頭にもつながる重要な転換点となりました。戦国時代の大逆転劇として語り継がれ、映画やドラマでもよく取り上げられる名戦です。
16世紀中頃、尾張(おわり、現在の愛知県)で勢力を拡大していた織田信秀(おだのぶひで)が亡くなった後、その息子である織田信長が家督を継ぎます。しかし、尾張の有力城主の一人であった鳴海城(なるみじょう)の山口教継(やまぐちのりつぐ)は、織田信長側に付くことなく、今川義元の側につきました。この裏切りの結果、今川義元は尾張の重要な拠点だった大高城を手に入れることになります。
織田信長はこれに対処するため、大高城と鳴海城の間の行き来を遮断しようと考え、複数の砦を築きました。これらの砦は、桶狭間の戦いの前後に、今川義元やその支配下の地域を監視し、防衛するために築かれたもので、戦局に大きな影響を与える重要な拠点となりました。
知多四国霊場巡礼においては、87番札所長寿寺(ちょうじゅじ)周辺の地域にあたり、桶狭間の戦いの遺構はお遍路道中の立ち寄りスポットとしておすすめなので、本記事で詳細に紹介したいと思います。
公園として整備されている「鷲津砦跡」
知多四国霊場87番札所長寿寺は、愛知県名古屋市緑区大高町にある臨済宗の寺院です。
知多四国霊場で唯一の名古屋市内に所在する寺院ですが、この地域は元々は知多郡大高町で、昭和39年(1964年)の市町合併により名古屋市に合併した経緯があります。
戦国時代には、長寿寺が現在ある地域一帯にいくつかの砦が築かれ、織田勢と今川勢がしのぎを削る最前線で、桶狭間の戦いの激戦地にもなりました。

桶狭間の戦いの際には長寿寺も戦火に巻き込まれ、焼失した歴史があります。
長寿寺の左側から背後にかけてに鷲津砦跡(わしづとりであと)があり、山門から西に約140m進むと到着します。

鷲津砦跡は、現在は綺麗な公園として整備されていますが、桶狭間の戦いの際には激戦地となりました。
鷲津砦は、この場所から南西約700mの位置の大高城が今川義元に攻略されたことに対抗するために、織田信長が丘陵の上に築いた砦です。
桶狭間の戦いが行われた当日の早暁、今川方の重臣であった朝比奈泰朝(あさひなやすとも)率いる約2,000人の軍勢が鷲津砦の攻撃を開始し陥落させたことが、桶狭間の戦いの前哨戦となったと伝わっています。
鷲津砦跡は現在は国の史跡に指定されるとともに公園としても整備されていて、戦国時代の歴史好きの人の間では有名な歴史スポットになっています。
国指定史跡の石碑がある「丸根砦跡」
また、長寿寺の山門を出て、県道50号線を東方面に約400m進み、左折し北方面に約50m進み右折すると丸根砦跡(まるねとりであと)に到着します。

県道50号線の長寿寺から東方向は歩道が整備されていて、歩きお遍路さんも歩きやすいです。
丸根砦は、大高城から東約800mの丘陵に先端部に築かれ、鷲津砦も含め大高城を包囲するように配置されました。当時の今川勢の基地であった豊明の沓掛城から大高城への支援路を見下ろす立地で、東西36m、南北28mの砦の周囲に幅3.6mの堀がめぐらされていたようです。
丸根砦は鷲津砦跡と同様に、現在では国の史跡に指定されています。

丸根砦跡の入口には名古屋市教育委員会が設置した案内看板がありました。

丸根砦跡中央部への急な山道を登っていくと、石碑がありました。
知多四国霊場87番札所長寿寺周辺の地域は、桶狭間の戦いで激戦地となり、その歴史を現代に伝える砦跡が国の史跡としてのこされています。知多四国霊場巡礼の途中に立ち寄って、地域の歴史を感じてみてください。
【「知多四国霊場87番札所長寿寺」 地図】
【「鷲津砦跡」 地図】
【「丸根砦跡」 地図】