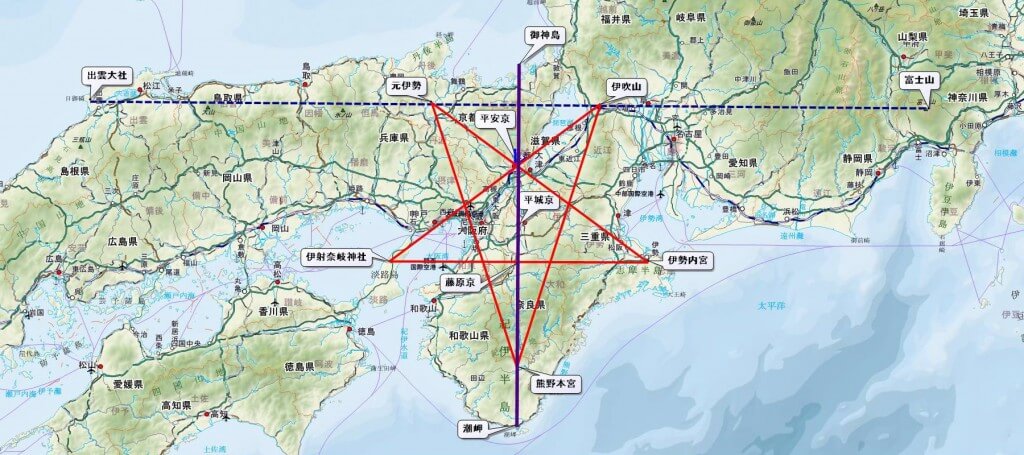遍路参拝で本堂・大師堂で勤行する前の準備は主に「灯明」「線香」「納札」「賽銭」がありますが、納札と賽銭の作法と意味について解説します。

—– 記事に登場する主な地名・単語
納札(おさめふだ)
賽銭(さいせん)
納札の意味
"おさめふだ" と読みます。
巡拝者の名刺に当たるもの。
紙製で「奉納 四国八十八ヶ所巡拝」など、字があらかじめ印刷されている物に、巡拝者自身の氏名等を記入して、寺院に置かれている所定の箱に収める。
しかしながら紙を用いるようになった歴史は浅く、近世まで木製のものが用いられてきた。木簡型の木札に所定の事項を記入し、寺院の堂宇や柱に釘を用いて打ち付ける。そのことから 四国遍路を回ることを "打つ" と呼ぶようになった(順打ち、逆打ちなど)。
現在は柱に諸札を打ち付ける行為はもちろん、堂宇などに納札・千社札等を貼る行為は固く禁じられている。
賽銭の意味
"さいせん" と読みます。
「お」を付けて、「お賽銭(おさいせん)」と呼ばれる方が一般的。
"賽" には 「神から福を受けた感謝を祭る」 の意味がある。
金銭として奉納するようになった歴史は、貨幣経済が浸透した中世以降であり、元々は海の幸や山の幸、米などが納められていた。
納札と賽銭、準備とあれこれ
お賽銭については、額に決まりはありません。
自身の感謝の気持ちやお願い事が実現して欲しい度合いに応じて、額を決めれば良いと思います。
また、寺社のトイレを使用した場合などは、普段より少し多目にお賽銭を入れるよう心掛けましょう。
初詣などでお賽銭を投げ入れる姿が見られます。
神社においては、勢いよく投げることで景気を付ける、「投げる=祓う」という考え方が存在します。
しかしながら、寺院では投げ銭はあまり好まれません。賽銭箱に近付いて、そっと静かに納めるようにしましょう。
納札は本堂・大師堂前にそれぞれ所定の納札箱が設置されているので、そちらへ納めるようにします。
その際、近くに置かれている写経箱と間違えないようにしましょう。
スポンサーリンク
※ 参拝の手順や解釈について、一般的な見解に基づき紹介しています。他にも様々な方法や解釈があることをご留意ください。
【遍路参拝作法その5】納札・賽銭の作法に関しては、以下の動画もご参考ください。
※遍路参拝作法の次の手順に関しては、以下リンクの記事に続きます。
※すべての遍路参拝作法のまとめと動画出演者の情報は、以下リンクの記事に掲載しています。
最近は、お遍路用品の品揃えが豊富なネットショップが増えてきていて、お遍路出発前にいろいろな商品をじっくり吟味して揃えることができるようになってきています。
10番札所切幡寺の参道で130年以上営業してきた歴史をもち、お遍路用品はもちろん、仏具や掛軸・表装などを取りそろえる「スモトリ屋 浅野総本店」のネットショップをご紹介しておきます。
https://www.rakuten.co.jp/sumotoriya/




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b6baf76.e11ea2d2.2b6baf77.ae003487/?me_id=1330970&item_id=10000081&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsumotoriya%2Fcabinet%2F22rk11.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)